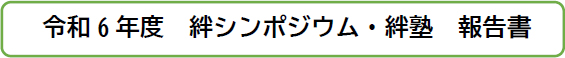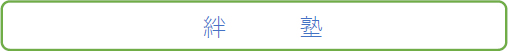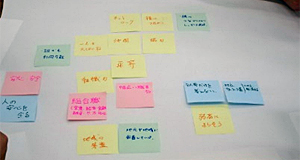|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||

|
去る12月16日(月)13:00より、JA福島ビル1001会議室を会場に、地産地消ふくしまネットが主催する「令和6年度絆シンポジウム」が開催されました。 全体で144名の参加でした。 今回のテーマは、「IYC2025福島県実行委員会キックオフイベント-協同組合がよりよい世界を築きます(Cooperatives Build a Better World)」でした。 そして、開催目的を国連総会は、2012年をIYCとして初めて宣言をしました。福島県内の協同組織や協同組織を支援する団体によって、2012国際協同組合年福島県実行委員会が発足しました。 掲げた目的と取り組まれた成果をもとに、協同組合の価値や協同組合が現代社会で果たしている役割等について、広く県民に認知されるよう取り組むとともに、異種の協同組合が連携することにより新たな価値を生み出し、もって、協同組合運動を促進させ、地域社会の持続可能な発展に一層寄与するために、本協議会が、後継組織として、活動を承継しました。 そして、国連総会は、2025年を2度目となる「国際協同組合年(IYC2025)」とし、2012年同様「協同組合はよりよい世界を築きます」(Cooperatives Build a Better World)をテーマとしました。2度目となるIYCの成功を目指して、ここにIYC福島県実行委員会のキックオフイベントを開催します。」としました。
最初に、副会長である福島県森林組合連合会田子英司会長より、開会のあいさつがあり、次いで、地産地消ふくしまネット会長であるJA福島五連管野啓二代表理事会長から、以下の内容の主催者あいさつがありました。 「令和6年度絆シンポジウムの開催にあたり、主催者を代表し、一言ご挨拶を申し上げます。本日は、年末のご多用のなか、県内各地から足を運んでいただき、誠にありがとうございます。また、日頃より当協議会の事業運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、来年、2025年は2012年以来2度目の“国際協同組合年”となります。 JA、漁協、森林組合、生協、労働者協同組合、労金、労済をはじめとする協同組合は、相互扶助の組織として持続可能な食料生産・消費、健康・福祉など、事業と活動を通じて持続可能な開発目標(SDGs)に貢献しています。 国連はこうした協同組合のSDGsへの貢献を評価し、その認知の向上と協同組合の振興を加盟国、国連そして協同組合関係者に促すために、昨年12月の総会において2025年を国際協同組合年とすることを宣言しました。 自然災害が毎年のように発生するような危機の時にこそ、”協同組合の精神”、”助け合いの心”は大きな力を発揮します。国際協同組合同盟は、世界112ヵ国300万組合、10億人の組合員を有しています。世界の協同組合の仲間とともに、「協同組合の精神」を広げる絶好の機会として、様々な取り組みをすすめてまいります。 全国組織の2025年2月のキックオフイベントに先駆けて、この後、本県としてキックオフを宣言いたします。 本日は、国際協同組合年に向けて、みなさんと認識を共有するため、日本協同組合連携機構から伊藤治郎常務理事にご講演いただいた後、協同組合統一のテーマとも言えます“食育”について農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課の堂脇義音(どうわき・あきと)様からご講演いただきます。 その後、食育の講演を踏まえ、生産者、消費者、行政、PTAのそれぞれの代表の方からパネル討議で意見交換をしていただく予定となっていますので今後の協同組合活動の参考にしていただければと思います。 結びに、今後とも福島県における協同組合間協同を発展させ、持続可能な地域社会づくりに取り組むことをお誓い申しあげまして、主催者の挨拶とさせていただきます。」 主催者あいさつのあと、2025年国際協同組合年(IYC2025)に向けてのキックオフとして、地産地消ふくしまネットの幹事長であるJA福島中央会の今泉仁寿常務理事より、IYC福島県実行委員会の「委員会構成(案)」「委員会規約(案)」「キックオフ宣言」がされました。
次に、IYC福島県実行委員会キックオフを記念しての基調講演①「2回目の国際協同組合年〜IYC2025にむけて〜」を日本協同組合連携機構(JCA)常務理事伊藤治郎氏にお願いしました。
次に基調講演②「食育の価値〜地域とともにつくる〜」を農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課課長補佐堂脇義音氏にお願いしました。
基調講演の後は、パネルディスカション「協同組合が取り組む食育について」を日本協同組合連携機構(JCA)加藤美紀主席研究員をコーディネーターに迎え、パネラーとして、JA会津よつば営農部ふるさと直販課農産物直売所「まんま〜じゃ」の石塚理璃愛さん、福島県生協連理事の池端美雪さん、喜多方市教育部学校教育課課長補佐の中野富全さん、PTAから安彦三枝子さんの4名の方々から、それぞれのお立場からの貴重なご意見をいただきました。 以下は、コーディネーターの加藤美紀主席研究員(以下「Co」)からいただいたパネルディスカッションのまとめです。 【本題(テーマの解釈)】 今回のパネルディスカッションは「協同組合による食育」をテーマに議論を深めた。 「食育」は、食に対する正しい知識や選択力を育むだけでなく、地域の食文化を継承し、持続可能な未来を築く重要な要素である。一方、「協同組合」は地域に根差し、つながりを生かして食育を実践する力を持っている。 本ディスカッションでは、4名の専門家パネラーと共に、協同組合や地域がどのように食育を通じてより良い未来を築くかを考えた。
PTA代表の安彦美枝子様の名札に間違いがございました。 正しくは安彦三枝子様です。たいへん失礼しました。 【議題と議論の内容】 テーマ① 未来を育む食育活動の今とこれから1.食育活動の実施状況 石塚さん 直売所では毎月「食育の日」に情報誌を発行しているほか、SNSを活用した情報発信を実施。 池端さん 組合員活動を中心に多様な食育活動を展開。核家族化や地域コミュニティの希薄化が進む中で、伝統的な和食の伝承や共食の機会提供に期待を寄せる。 中野さん 朝食欠食率の調査を実施。県内と比較して欠食率が高く、子どもの食育が特に重要だと指摘。 池端さん・安彦さん 家庭での朝食状況を共有。「アイデアや工夫を持ち寄ることで新しい解決策が生まれる可能性がある」と提案。 2.安心・安全の取り組み 安彦さん 娘のアレルギーをきっかけに食の安全・安心に関心を持つ。生協の食品表示は詳しく信頼できるとし、地域の安心・安全な農産物を購入するよう心がけている。 石塚さん 直売所における農産物の安全確保について、生産者の意識を高める取り組みを報告。 3.郷土料理の継承 安彦さん 県のイベント「ふくしまっ子ごはんコンテスト」に参加し、子どもの成長を実感。家族で郷土料理や地域の食材を共有する機会になった。 石塚さん 直売所では、生産者が手作りの伝統料理を販売し、手軽に郷土料理を楽しめるよう支援。 池端さん 家庭での郷土料理の実践について言及。「相談できる人がいることや、手作り料理のおいしさを知っていることが大きい」と強調。 中野さん 農業科の取り組みを紹介。小学生が生産から料理まで1年を通じて学び、地域の生産者が関わることで自然と食文化が伝わっている。 →Co「深い学びにつながる素晴らしい取り組み」と評価。 地域と学校の協力が相乗効果を生み出す好例だとし、「関心のない層にも関心を持ってもらう仕掛けが今後の課題」と提案。 テーマ② 学校給食から見た地産地消と食育の可能性学校給食を通じた次世代への食育の役割について議論。 石塚さん 直売所では学校給食に食材を供給し、その食材を直売所でも購入できる仕組みを構築している。 → Co「学校給食で使われる食材が直売所で購入できることは、学校と家庭をつなぐ素晴らしい取り組みだ」と評価。 中野さん 熱塩加納方式の学校給食では地場産食材や調味料にこだわり、質の高い給食を実施している。また、これを市内全体に広げる取り組みを行っている。 学校給食基本方針では、以下の目標を定め、質の向上に取り組んでいる。 地場産食材の使用率向上、環境にやさしい農産物の活用、給食が「美味しい」と回答する生徒の割合の向上 → Co「学校給食が生きた教材として活用される好例であり、食育を組み込むことで経済事業と地域貢献の両立が実現できる」と指摘。 テーマ③ 協同組合の連携が生み出す新しい食育モデル協同組合が連携し、地産地消の価値を最大化する新しい食育の形について議論。 1.協同組合に期待すること 中野さん 地域に根付いた産業を行う協同組合には、その取り組みを子どもたちに伝えてほしい。それが郷土愛の醸成につながる。 安彦さん 協同組合には、安心・安全な食の提供を期待している。 2.国産協同組合年プレ企画「LOVEで始めよう」と「大豆の会」 池端さん 「LOVEで始めよう」 生協・農協・漁協という異なる協同組合が一堂に会し、活動の共有や意見交換を通じて、より良い地域づくりに向けた新たな連携の可能性を考える取り組み。 「大豆の会」 遺伝子組み換え大豆の輸入を背景にスタートした取り組み。食と農を結ぶ地域システムとして展開し、生産から消費に至るまで関わる人々が有機的につながることを重視している。また、生産を担う農家には、再生産可能な価格を設定していると報告。 → Co「同じ目的を持つことが重要。各組織が得意分野を持ち寄り協力することで、新たな可能性が生まれるのではないか」と指摘。 テーマ④ 地域課題を解決するための協同組合の役割日本の未来にとって重要な「食料自給率」を中心に議論を行った。 現在、日本の食料自給率は38%(カロリーベース)にとどまっており、輸入依存の食生活が当たり前になることで、食の選択権や安全性の制限や農業・漁業が疲弊するリスクが高まっている 【議論の内容】 石塚さん 直売所では地域の食材供給を支え、生産者の農産物を購入できる場を提供している。現在、生産者全体は減少しているものの、「まんま〜じゃ」の出荷者は増加傾向にある。 要因は、自分で価格を設定できること、消費者の喜ぶ姿を実感できることが生産者のやりがいにつながっている。 →Co まんま〜じゃが魅力的な農業を実践する場として機能していることが、地域の供給力向上につながっていると評価。 池端さん 地域の自給率向上には「買い支える意識」が重要だと指摘。 →Co 価格優先や環境負荷への無関心な消費行動が見られる中で、持続可能な活動を応援する消費者の存在が心強い。 安彦さん 食料安全保障や食料自給率は大きなテーマに感じるが、農業体験を通じて生産の現場を知ることで、「自分ごと」として捉えられるようになる。地域で手軽に農業体験ができる場があるとうれしい →Co 「買い物が社会を変える」という視点を広げ、未来を支えていることを実感できる仕組みが必要だと強調。 【質疑応答】 北条さん 地域を同じくする喜多方市の中野さんへ、「ぜひ仲間になって一緒に活動したい」という温かいメッセージが寄せられた。 パネルディスカッションのテーマ「協同組合が取り組む食育の可能性」を通じて、次の点が明らかになった
本ディスカッションでは、具体的なアイデアが多数共有された。 これらを具体的なアクションにつなげ、さらに発展させることで、協同組合が中心となり、より良い未来を築けると確信している。 最後に、地産地消ふくしまネットの副会長である福島県生協連佐藤一夫代表理事会長から閉会のあいさつがあり、終了しました。
翌2日目、12月17日(火)10:00より、JA福島ビル1002会議室を会場に、地産地消ふくしまネットが主催する「絆塾」が開催されました。 県内から14組織27名が参加しました。 進行役に、 JCA協同組合連携1部亀田篤子さんを迎え、「国際協同組合年のことを学び、皆さんが何かやってみようと思っている」をゴールに、7班に分かれてグループワークを行いました。
| |||||||||
|
|||